飼い主様へ
- HOME
- 飼い主様へ
フィラリア

フィラリア症とは?
フィラリア症は蚊によって感染し、ワンちゃんの命にかかわるとても怖い病気です。
蚊は私たちの生活の中で普通に見る生き物で、フィラリア症はとても身近ないつ感染してもおかしくない病気です。
病気の予防を確実にして、大切なワンちゃんをフィラリアから守りましょう!
フィラリア症の予防方法
フィラリア症は月1回の投薬で予防できます。
フィラリアのお薬は、飲んでから1ヶ月間効果が続くというわけではありません。
1ヶ月前にワンちゃんの体内に入り込んだ、少し成長した感染仔虫をまとめて駆除するお薬なので、蚊が活動始めた1ヶ月後から蚊を見かけなくなってから1ヶ月後までしっかり予防する必要があります。
蚊は平均気温が15℃以上で吸血すると言われていますので、15℃以下になるまでは予防しましょう。
また1回の注射で1年間効果が持続する予防法もあります。
血液検査
予防する前に、フィラリアが感染していないことを確認するために血液検査が必要です。
フィラリアに感染している状態で予防すると副作用が出てくる恐れがあります。
・血中のミクロフィラリアが死滅することで体内に異物があると、認識し排除しようとするアレルギー反応。(アナフィラキシーショック)
・死んだミクロフィラリアが血液に乗り、様々なところで塞栓して起こる筋肉痛、発熱、急性腎不全、血液循環不全など。
・お薬が心臓に寄生している成虫に作用すると成虫が死んでしまい、大静脈に詰まり大静脈症候群を起こしてしまうことがあり、大変危険な状態になります。
僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁閉鎖不全症とは?
僧帽弁閉鎖不全症とは、心臓が肥大化したり僧帽弁が変形を起こしてしまった結果、しっかり僧帽弁(血液の流れを防ぐ働きをする弁)が閉じなくなり、全身に送り出されるべき血液の一部が心房内に逆流して起こる病気です。
僧帽弁閉鎖不全症を起こすと血液が肺へと逆流し、血液の循環が悪くなり肺が、うっ血(血液が充満して局所の血液量が増加した状態)して呼吸がうまくできなくなります。
発症するときには、主に乾いた咳や呼吸困難などの症状が現れます。犬の僧帽弁閉鎖不全症は、老齢期の小型犬に多くみられます。
慢性腎臓病

慢性腎臓病とは?
慢性的で元に戻ることなく進行していく腎臓の機能低下のことです。
一度壊れてしまった腎臓を元に戻すことはできません。
また、残っている正常な部分へ壊れてしまった分の負担がかかるため、ある一線を越えると一気に病状が進んでしまいます。
しかしながら早期発見とその後の食事管理により、延命が期待できる病気でもあります。
腎臓病の症状
食欲不振、嘔吐、体重減少、下痢、毛づやが悪くなる、味の好みがよく変わる、進行すると低体温、口内炎、ケイレン、昏睡状態、尿毒症(体に老廃物がたくさんたまった状態)など。
また、赤血球の産生を促すホルモンが作られなくなり、貧血になってしまいます。腎臓の濃縮機能が衰え、色・臭いの薄い尿が大量に排泄されます。そのため脱水になり、お水をよく飲むようになります(多飲多尿)。
このような場合、腎臓の75%はすでに機能していません。残った腎臓の機能をこれ以上悪くしないように点滴をします。脱水の改善、水分のないドロドロの血液をサラサラにします。
お問い合わせCONTACT
大阪府茨木市にあるハロー動物病院は、ワンちゃん、ネコちゃんを専門で診察しています。
当院へのご予約はお電話またはWEB受付からお願いいたします。
072-625-6409
[診察時間]9:00~12:00 / 17:00~20:00
[休診日]木曜日、日曜日午後、祝日午後
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 |  |
 |
 |
/ |  |
 |
 |
| 17:00~20:00 |  |
 |
 |
/ |  |
 |
/ |
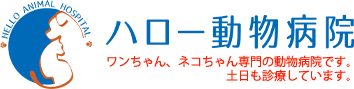


 072-625-6409
072-625-6409
 WEB受付
WEB受付